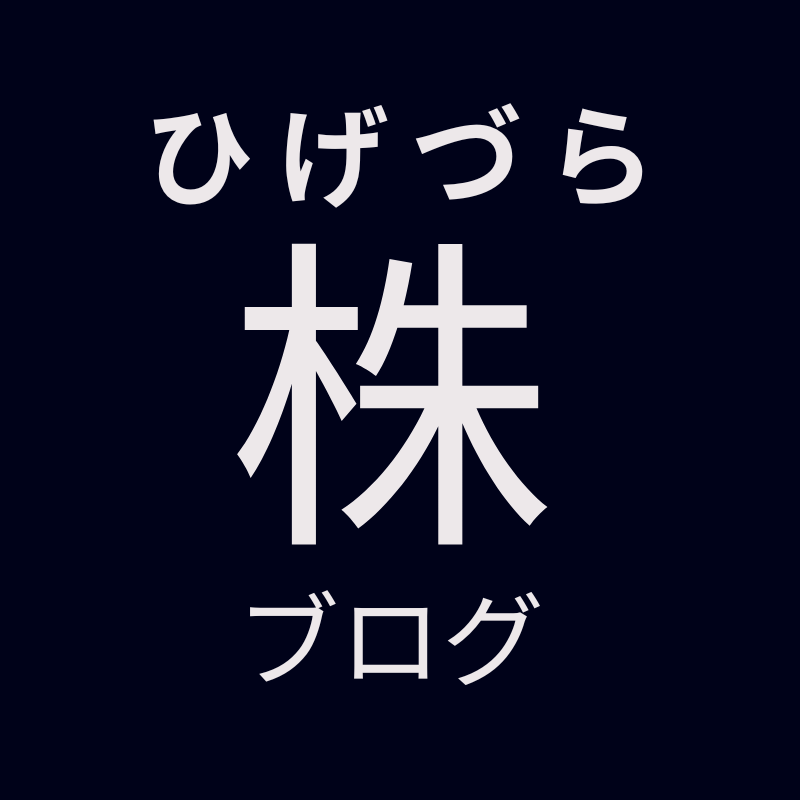どうも、ひげづら(@higedura24)です。
株式市場では年に数回ほど大きな暴落局面があります。
暴落といってもその規模は様々で、1週間ほどで回復するケースもあれば売りが売りを呼ぶ雪崩のような展開もあるでしょう。
売りが雪崩になるケースでは投資家心理が混乱に陥っていることもあり、株式市場や先物市場の値動きに大きく影響します。
サーキットブレーカー制度とはそういった「投資家心理が売りもしくは買い一辺倒になる状況を抑える」といった仕組みで、市場の秩序をある程度守るものです。
この記事では
- サーキットブレーカー制度の概要
- サーキットブレーカー制度後の市場推移
について書きました。
簡単な内容だけでも知っておいた方が良い市場の仕組みですので、ぜひご参考ください。
サーキットブレーカー制度とは
サーキットブレーカー(Circuit breaker)制度とは先物やオプションにおいて「市場の値動きが一定以上になった場合に取引を強制停止し、再開後は制限値幅を拡大する」という仕組みのことです。
外部参照リンク:Wikipedia|サーキットブレーカー制度
例えば投資家心理が売りに傾き過ぎた状況を強制的に小休止させることで緩和し、
- 本当に売るべきか
- 売るにしても慌てて売るべきか
- 売りではなく値動きが落ち着いた段階で買うべきか
など一度冷静になって選択肢を考えてもらう目的があります。
「サーキットブレーカー」の語源は電気回路に組み込まれた安全機構からきていて、本来は過度の電流で強制的な電源オフがなされるシステムを言っているようです。
国内では1994年2月14日から導入されており、
- 株価指数先物取引:一定の変動幅を超えて上昇もしくは下落が起きた場合に取引を10分間停止
- 債権先物取引:先物価格が基準価格から2円以上変動した場合に取引を15分間停止
といったルールになっています。
中断対象は、サーキットブレーカー発動時に
- 日経225先物の全限月
- 日経225miniの全限月
- 日経225オプションの全銘柄
- ①~②に関連するストラテジー取引
- ①~③に関連するJ-NET取引
が連動中断される仕組みです。
具体的な発動条件の例としては・・・

外部参照リンク:JPX|サーキットブレーカー発動イメージ(PDF)
- 制限値幅の上限価格に1分間張りつき ⇒発動
- 上限価格で約定後、1分間上限から一定範囲内で約定 ⇒発動
- 制限値幅の上限で約定したものの、数秒後に一定値幅より下落 ⇒発動しない
- 上限価格で約定してもみ合ったが、1分以内に一定値幅より下落 ⇒発動しない
となっています。イメージ図のポイントは
- 上限値幅で約定
- 上限から一定値幅で推移
- 推移が1分間続く
といった点で、簡単に言えば上限もしくは下限の行き過ぎた範囲で値動きが続くと発動するという流れですね。
サーキットブレーカー制度による制限値幅の拡大は2回まで行われ・・・

先物(上)とオプション(下)で違ってくるようです。
中断対象や制限値幅についての詳細はJPXにて公表されていますので、一度確認してみると良いでしょう。
ちなみに、再開は制限値幅を拡大のうえ板寄せ方式で行われるルールです。
サーキットブレーカー発動後の日経平均株価推移
サーキットブレーカー制度が発動した例としては
- 2008年10月10日:リーマンショックを発端にしたアメリカの金融安定化法案が否決
- 2011年3月14日:東日本大震災をきっかけに発動
- 2016年2月9日:マイナス金利導入で日本国債の長期金利がマイナスになった
などが挙げられます。
これらのタイミングでサーキットブレーカーが発動したあと、日経平均株価がどうなっていったかを見てみましょう。
リーマンショック時の発動例
まず2008年10月10日のサーキットブレーカー発動例からです。

リーマンショックはサブプライムローン問題発覚から下げていたので、最後の雪崩というイメージですね。
青枠部分でサーキットブレーカーが発動し、そこから年が変わるまでもみ合いが続いています。
ただ、そこからは徐々に株価が戻り、8000円を割れた状態から11500円まで上昇する結果になりました。
東日本大震災時の発動例
次に2011年3月14日の東日本大震災時にサーキットブレーカーが発動した例です。

東日本大震災時は大きく下がることになりましたが、週足では大きな下髭を引いたあとに株価がじわじわと上がりました。
その後は下げてますが、また高値に戻るボックス推移になっていますね。
マイナス金利導入時の発動例
最後にマイナス金利の影響で日本国債の長期金利がマイナスになった時のサーキットブレーカー発動例です。

大きく陰線を引きましたが、その後は反発して株価が戻っていますね。
年末に向けて大きく株価が上がっていますが、これはトランプ政権誕生によるものです。
サーキットブレーカーは最後の暴落で生じるもの?
代表例を3つ取り上げましたが、サーキットブレーカーが発動された時期を過ぎれば株価が上がっているように見えます。
これはサーキットブレーカーの発動が「投資家の狼狽売り」に起因しているからでしょう。
投資家が心理的にコテンパンにやられてしまうと、市場では売り叩かれます。
それが先物などの暴落となって表れるわけですが、売りが出きったあとは大なり小なり上がるしかないのかもしれませんね。
サーキットブレーカーが発動されたというニュースを受けたら、売りが打ち止めになる可能性もあるでしょう。
ちなみにこの記事では3例で考えてますが、
- 2001年9月12日:アメリカ同時多発テロの翌日
- 2013年:アベノミクス相場の反動
でサーキットブレーカーが発動したあとも株価が反発していました。
絶対はありませんが地合いの反発を前提に考えてみると面白い見方ができそうです。
各国のサーキットブレーカーについて
サーキットブレーカーは元々アメリカの株式市場で生じたブラックマンデーがきっかけでできた制度です。
したがってアメリカにもサーキットブレーカー制度はあって、日本はそれに追随して導入した形と言えます。
ちなみに、アメリカで起きた世界同時多発テロでは事件後の1週間において取引が中止された事件もあったようです。
これはサーキットブレーカーとは別物でしょうが、中々ないことなので株式市場の歴史として大きな事件ですね。
中国では2016年1月4日に導入したものの投資家からの反発が強く、問題となった経緯があります。
反発の原因ともなった中国市場のサーキットブレーカーの特徴は
- 7%以上の下落でその日の売買はそれ以降中止となる
- 現物株にも適用される
といった点です。
制度導入の1月4日に続いて、1月7日にもサーキットブレーカー発動となり市場がかなり混乱しました。
投資家を守るための制度が売り煽るこになっていると批判が大きく、わずか4日の導入で制度撤回となりました。
これが原因で世界同時株安も引き起こされたので、中国だけでなく世界を巻き込んだ珍事件と言えますね。
まとめ
いかがでしたか?今回はサーキットブレーカー制度についてご紹介しました。
投資家を守ってくれる制度ですので、簡単にでも覚えておいてはいかがでしょうか。
過去の傾向としてはサーキットブレーカー発動で一度売り止む可能性もありますし、関連ニュースには気を配っておいて損はないですね。
関連記事には
がありますのでご参考ください。それではまた!