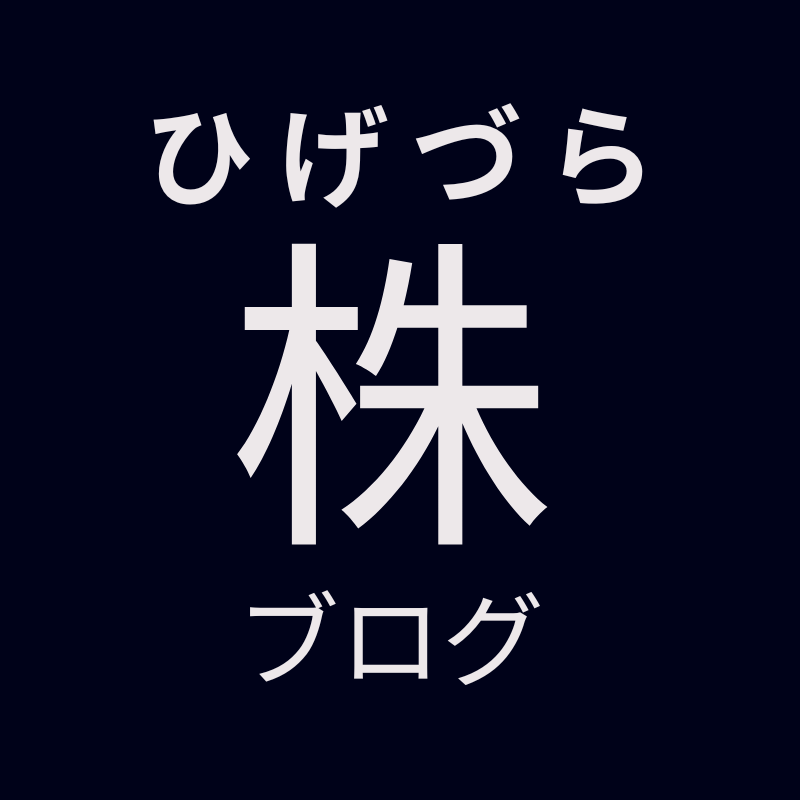株をやっていると「買い戻し」という言葉を聞くことがありますが、皆さんはこの本当の意味をご存じですか?
単に売ってしまった株を再度手元に戻すという意味で使われていることもありますが、実は厳密に言うとこういった意味で使われる言葉ではありません。
この記事では買い戻しという言葉に含まれている複数の意味をなるべくわかりやすくご紹介し、その実例チャートを掲載しました。具体的には
- 空売りの買い戻し
- 利確後の買い戻し
について述べています。会話の中で意味がなんとなく伝わっていればそれで良い気もしますが、知識として知っておいた方が良いことだとは思いますのでぜひご参考下さい。
ちなみに空売りの買い戻しができないケースについても触れています。
株の買い戻しをわかりやすく解説
最初に読み方ですが、買い戻しは「かいもどし」と読みます。また、この買い戻しをわかりやすく説明するためには
- 現物買い
- 信用買い
- 信用売り(空売り)
について簡単に述べておかなければなりません。
まず現物買いとは「自分の手元資金にて株を購入すること」です。自分のお金で買っているので株の名義はあなた自身であって、自分が持ちたい期間だけずーっと保有することができます。
それに対し信用買いは「証券会社にお金を借りて株を購入すること」を指す言葉です。証券会社に借りたお金は定められた期限までに返済する必要がありますが、自分の資金の2倍や3倍もの株を保有することができます。
最後に信用売りですが、これはお金ではなく「株を借りて売ること」です。初心者さんからすると「株を借りて売ってお金がもらえるの?」と感じるかもしれませんが、厳密には
- まず株を借りて売る
- 株価が下がって自分が売った値段よりも下になったタイミングで買い戻して証券会社に株を返す
- 最初の売却価格と買い戻し価格の差額を利益として受け取る
という手順になります。当然、株価が上がってしまったところで買い戻した場合は損失となるので注意が必要ですね。
おや?上記の流れの中に「買い戻し」という言葉が出てきました。
そうです、株の世界における買い戻しとは「信用売りした株の買い戻しを行う」という意味が込められているんです。戻すというからには元々あった株を手元に戻すという意味が連想されますが、これは現物株を買い戻すという意味ではなく信用売りのこと。
ちなみに信用売りは一般的に「空売り(からうり)」と呼ばれていて、買い戻しと聞いたら「空売り決済のことだな」と考えて頂いて構いません。ただ、個人的には買い戻しがどのような局面で行われたのかが大事だと考えていますので下記にそれを記しておきます。
下げたあとの空売り決済(ショートカバー)
空売りがよく行われる場面のひとつに下げ相場があります。なぜなら空売りは株価が下がるほど利益が出る売買なので、下方向にトレンドが発生していると順張りという考え的にも売買ボタンを押す心境的にもやりやすいからです。
極端に株価が上昇してしまった状況で逆張り売りするということも考えられますが、普通は下げ相場で空売りするものだと考えています。
一般的に株価というものは一方的に下げたり上げたりはしません。必ず定期的に逆方向に進む動きがあった後に再度メイントレンド方向に進むわけです。勘の良い方はわかるかと思いますが、下げ局面で生じる戻しの動きこそが「空売りの買い戻し」ということですね。

例えば上記のような強い初動で下げ始めたチャートでも、赤枠部分のように途中でリターンムーブが入るということはしばしばあります。黄色丸で示したような最初の強い下げの中には
- 慌てて保有株を売った人
- 下げ始めを狙った空売り
という2つの推進力が合わさっているので勢いが上がっていると考えられますが、どちらかと言えば弱い値動きであるリターンムーブには「この辺で買い戻しておくか」という考えがほとんどなので全戻しとなるわけではないのです。
したがって、この空売り決済による買い戻し(いわゆるショートカバー)は買い向かうところではありません。買い向かうことを考えるのはもっと底打ち感が出た局面であって、二番底を待つ場面などが有名でしょう。
材料の出現によって違う需要がその株に生まれれば新たな買い勢力がきてくれるという状況も見込みやすいので、チャートだけではなく企業が出す情報にも着目した方が良いですね。上記のチャート例では・・・

この赤枠部分で新たな材料が出たため大幅ギャップアップとなり、トレンド転換への期待が高まるチャート状況へと変化しました。おそらくここでは先ほどと違い
- 慌てて空売りを買い戻す人
- 新規材料で買い向かう人
の2つの推進力が働いたためにギャップアップしたのでしょう。
天井圏での踏み上げ
前述のショートカバーによる買い戻しをわかりやすく言うと「空売り勢の利食い」が連想できましたが、実は株価の高値圏でも買い戻しは起こります。
それはいわゆる「踏み上げ」というもので、こちらは「空売り勢が耐えきれないほど株価が上がってしまったために起こる損切り」という意味合いです。

例えばこちらの週足チャートでは株価が勢いよく上がっている様子が見受けられます。初動からかなり上がってもさらに高値圏を目指すこういった値動きは「空売り勢が買い戻しを余儀なくされて(踏み上げられて)いる様子」ですね。
こういった天井圏での買い戻しでは強い下げ相場と同様に
- 強気に高値圏で株を買う人
- 空売りの損失に耐えられず買い戻しを行う人
という2つの推進力が働くので勢いがつきやすいと言われています。ただ、こういった踏み上げ相場は滅多に起こるようなものではなく
- 株価上昇前に下げ局面があったことで信用売りが増加していた
- その状態で株価が上がったため信用売残(決済されていない空売り)が大量にある
といったことが大前提でしょう。上記のチャート例でも
- 信用買残:出来高欄にある赤線
- 信用売残:出来高欄にある水色線
を比較すると倍以上も信用売残が多い状況のまま株価が上がっていたことがわかりますね。
株の世界では信用買残より信用売残が多い状態を「売り長」と呼んでいて、踏み上げという意味での空売り買戻しが起こる前提状況と考えられています。売り長では信用倍率が1.0倍を切りますので、踏み上げが心配であれば該当状況での空売りは避けた方が良いでしょう。
ちなみに空売りしたい人が殺到して証券会社側の株式調達が困難になった場合、逆日歩という追加コストが生じます。逆日歩はひどい時には100株で万単位のコストが生じますので、空売り勢からするとかなりきついものです。したがって、売り長と同様に逆日歩も買い戻しをさせやすくする要因なので信用倍率と併せてチェックしておきましょう。
逆に言えば踏み上げ相場を狙うという観点では上記2点はひとつの目安となり、これらに加えて
- 機関投資家や個人が空売りを買戻したくなるほど大きな材料
- 低時価総額
といった条件も欲しいところです。こういった複数の条件が上手い具合に合致して初めて踏み上げ相場による買い戻しが起こるのではないかなと思います。
空売りの買戻しができないケースとは
ところで空売りの買い戻しをしたくてもできないケースというのが中にはあります。それは「寄らずのストップ高」になってしまったケースですね。寄らずのストップ高とは
- あまりに買いが殺到したことで当日中に値がつかない状態
- 当日の最大上限値幅まで気配値が上がって大引けを迎える
- 当日終値で空売りを買い戻しできるかは抽選次第になる
というものです。
空売りを買戻しできないケースはこの寄らずのストップ高が最も有力で、抽選に外れた場合は翌営業日に自動的に持ち越されます。ちなみに抽選になってしまう理由は「買い手に対して売り手が圧倒的に少ないから」です。
例えば時価総額100億円の企業に売上高100億円の案件が出てきたら市場はどう感じるでしょうか。単純計算で時価総額が2倍、つまり株価も2倍になると考えられてほぼ確実に買いたいと感じる投資家が殺到しますよね?
株の注文は売る人と買う人どちらもいなければ成立しません。だからこそこういった状況では値がつかないまま気配値だけが上限値幅まで昇ってしまうわけで、これ以上損失が拡大しないよう空売りを買い戻したくてもできない状況になります。
抽選の結果として買い戻しができれば良いのですが、強い材料だと翌営業日もそのまた翌営業日も買い戻しができないまま含み損拡大を眺める・・・ということもあり得るでしょう。ですから時価総額が低い貸借銘柄を空売りする場合は十分に気を付けなければなりません。
利確した株を買い戻しても良いか
一般的な株の買い戻しに関する解説はこんなところです。しかし、冒頭で述べたように空売りの買い戻しという意味ではなく「一度売った株を買い戻した」という意味で使っている方もいらっしゃるでしょう。したがって、ここでは利確後の買い戻しについても考察してみたいと思います。
まず一度利確した株を買い戻すという場面では「やっぱり株価が上がりそうだから保有を続けよう」という考えがありますよね。皆さんも苦渋の決断として売ったものの、値動きが気になって監視は続けていたという経験ありませんか?
利確後に迷うケースに限って株価が大きく上がったりするものですが、果たしてそこで考えを曲げてまで買い戻すことは良いことなのでしょうか。結論的にはあまり良いことではないと私は考えていて、理由は「一度それをやってしまうと癖になるから」です。
個人投資家の采配は自分一人で決められるというのがメリットでもありデメリットでもあります。どのような売買結果になろうとも自分だけに責任があって、それは売買方針をいかようにも曲げられるということです。確かに利確後に悩んだ挙句買い戻したということは私もあります。しかし、利確の前段階で迷いを断ち切って売買に踏ん切らないといけないという側面もあるわけです。
通常、一度決断をして実行すれば本来ならそこで一旦は話が終わりというか「次の銘柄に目を向ける」という姿勢になります。それなのにそこでまた買い戻すということを行ってしまっては話がどこまでも続いてしまいますし、同じことを違う銘柄でも行ってしまうでしょう。
優柔不断な売買癖が定着してしまうと良いことはないので、例え利確後に株価が大きく上がっても買い戻しは行わない方が長い目で見たときに自分のためになると思います。
ちなみに利確後にすぐ買い戻しを行うくらいなら買い増した方がまだ健全です。ただし、勘違いしてほしくないのは「一度利確した銘柄は2度と買わないわけではない」という点ですね。
感情的に「やっぱり上がりそうだから買い戻したい!」となるのはいけませんが、「株価がある程度下がったところで戦略的に買い戻し」というケースはあります。この時のポイントは「売却時と買い戻し時では状況が変わっている」ということで、値動きフェーズが進んだことで新たな買い場を探せているのであれば問題ありません。
利確という判断をすぐにねじ曲げることはおすすめできませんが、粘り強く監視を続けて再度利確できるような状況を見つけるのはありでしょう。
まとめ
今回は株の買い戻しについてなるべくわかりやすく解説しました。一般的には空売り決済を表す言葉として使われ、代表的なのはショートカバーと踏み上げという2つの局面です。ショートカバーは弱い動きなので乗るべきではありませんが、底打ちやトレンド転換が期待できそうな状況に変化した場合は乗っても良いでしょう。
踏み上げはそれ自体が滅多に起こることではないですが、もし期待できる場面であれば乗っても良いと考えています。
また、中には買い戻しを「単純に売った株を買い戻す」という意味で使っている方もいます。例えば利確した株をすぐに買い戻すことはおすすめできませんが、状況変化を監視した末に新たな買い場として買い戻しを行うのはありですね。
人それぞれ色々な買い戻しがありますが、うまく利益が出るように冷静な売買を心がけたいものです。