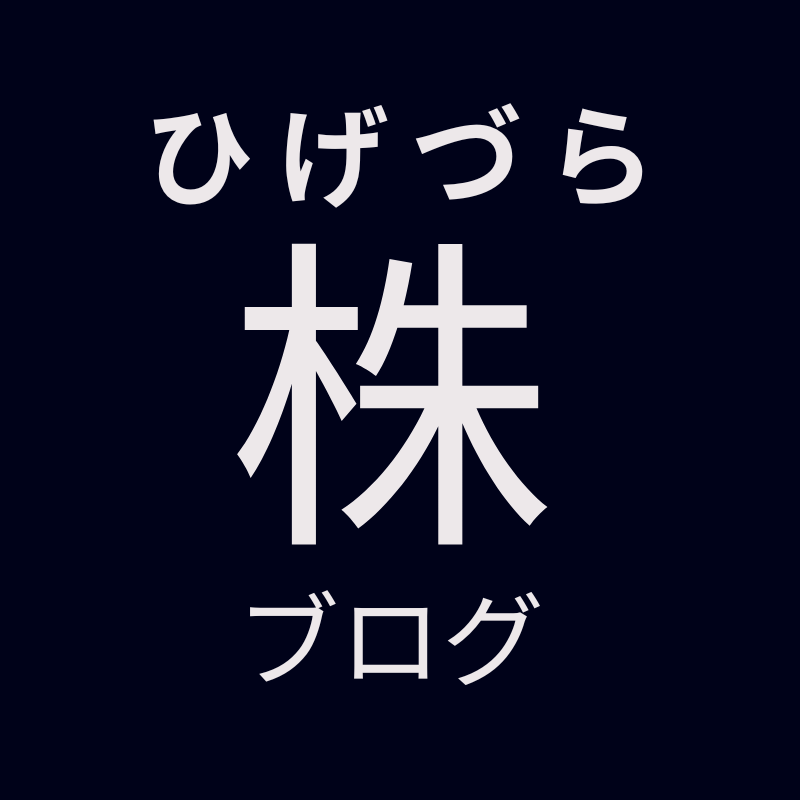株式市場が寄りつく際につけられる価格、それが「始値」です。例えば日足の始値であれば「その日がどんな相場になりそうか」を考えるための重要な株価とされています。
始値は直近の節目価格などと比較すると色々なことが読み取れ、推移を追うことでも値動き考察が行えるでしょう。そこでこの記事では始値の
- 読み方
- 決まり方
- 意味合い
について書きました。
始値なんてそこまで気にしていないよという方はぜひご参考いただき、チャートを見る際に実践してみて下さい。
始値の決まり方と読み方
最初に「始値」の読み方をお伝えしておきます。よく「はじまりね」など色々な勘違いをされることが多い始値ですが、正式には「はじめね」と読むので覚えておきましょう。
また、始値は日足に限って「寄り値(よりね)」とか「寄り付き値(よりつきね)」と表現されることもあります。これは言葉通り、当日に寄りついた株価を示していて、そのローソク足がどこから始まるのかを教えてくれるわけです。
外部参照リンク:SMBC日興證券|始値(はじめね)
では始値はどのような決まり方をしているのでしょうか?株価の約定方式には以下の2種類があります。
- 板寄せ方式
- ザラ場方式
ザラ場方式は成行注文や指値を最良気配で約定させていくだけなので皆さんおわかりでしょう。しかし、始値や終値を決める際に取られているのは「板寄せ方式」の方です。
板寄せ方式とは
始値がどこに決まるのかは「ザラ場が始まる前の注文状況」に影響されます。株式市場では午前8:00から注文受付を開始しますが、実際に約定するのはザラ場開始の午前9:00以降です。
そういった色々な価格に約定していない注文が置いてある状況で行われるのが板寄せ方式なんですね。以下に、板寄せ方式の3つの条件を楽天証券から引用しておきます。
【条件1】成行の売り注文と買い注文すべてについて約定すること
【条件2】約定値段より高い買い注文と、約定値段より低い売り注文がすべて約定すること
【条件3】約定値段において、売り注文または買い注文のいずれか一方すべてについて約定すること
外部参照リンク:楽天証券|約定の仕組み
板寄せ方式では上記の条件を満たすように
- まず売り注文と買い注文の累計数が逆転する価格を始値と仮定する
- 次に売り成り行きと買い成り行きを約定させる(差し引きでどちらが多いか)
- さらに売り指値と買い指値を約定させる
- 売りか買いのどちらかが全て約定している状態にする
といった手順で価格を決めます。この板寄せ方式からわかることは
- 売りも買いも寄り付きの時点で参加している投資家の意図が含まれている
- それらを全て合計した結果で始値や終値が決まる
ということです。これは始値の意味合いを考える上で非常に重要な考え方となります。
始値の決まり方から考える重要性とは
始値は板寄せ方式という「寄り付き前の注文を合算する方法」で決まります。このことからわかるのは
- 多くの注文を集めた結果のため、大きな出来高となる
- 市場の総意と前日終値にどれだけ差があるか
ということです。
まず前者について。これは分足を見ていただければわかることですが・・・

このように始値をつけたローソク足の出来高は非常に多くなる傾向があります。また、これによって大きく影響されるテクニカル分析の考え方がありますよね。それは
- 価格帯別出来高:どの価格帯で約定した出来高が多いか
- VWAP:当日の約定平均価格を出来高加重したもの
のふたつです。
始値の出来高が爆発的なものになるということは「当日に約定した数が多い価格帯を考える際には始値がベースとなってくる」わけです。また、そこから「ザラ場中の実質的な(出来高加重した)平均約定価格」を考える際にも基準となってきますよね。
価格帯別出来高やVWAPを考える理由は「値動きの抵抗帯や支持帯を探す」というものですので、始値は間接的にここにつながってくるわけです。例えば・・・


同じ値上がり率ランキング上位の銘柄でも、
- 上のチャート:始値やVWAPを割り込まない
- 下のチャート:始値やVWAPを割り込む
という違いによって値動きの印象が全然違いますね。
よく「日足が陽線の日にデイトレしよう!」なんて意見がありますが、あれはこういった考え方に関連しているものだと思います。日足で見たときに陽線なら始値より上で、陰線なら始値より下でザラ場推移するということ。
買いなら陽線が良いですし、売りなら陰線が良いというわけですね。ただし、その時は日足が陽線(陰線)であってもザラ場中の値動きで陽転(陰転)します。そのときに考えるのが始値をつけた際のローソク足であり、そこは値動きの急所となりかねません。
次に「始値(市場の総意)と前日終値にどれだけ差があるか」という点について。始値は板寄せ方式により全ての注文を約定し終えてから決定されます。これは言い換えると「寄り付き前における市場の総意を株価に反映した」ということではないでしょうか。
この市場の総意には様々な意味が込められていて、
- 個別銘柄の決算内容や新規材料
- NYダウや為替の状況
- 業種に関するニュースや思惑
などが挙げられます。例えばその結果として、
- 前日終値より窓開け上昇で寄り付いた
- 前日終値より窓開け下落で寄り付いた
となったらどうでしょう。おそらく窓開けの理由がわからないホルダーでも「今日は強い値動きだからイケイケ!」とか「今日は弱い値動きだからダメダメ・・・」と思いませんか?
そこから派生して陽線(陰線)のなりやすさにも影響がありそうです。実際に日足を見たときに新高値をつけるかどうかの大事な局面で「翌営業日の始値が新高値で寄り付いた」となった場合はかなり高い確率で始値から上へ伸びる値動きが出ます。

上記は4500円の大きな節目かつ上場来高値という抵抗をしばらく超えられなかったという日足を出しています。注目してほしいのは最後から2番目の大陽線です。
よく見るとこの大陽線は始値の時点で今までの抵抗帯を超えているのがおわかりでしょうか?これはつまり「市場の総意として寄り付きからそろそろ新高値に行っていいよねとなってきた」という意味です。こういったパターンは始値から上に伸びることが多いので覚えておいた方が良いと思います。
また、前日までの流れが底打ちや天井圏を表すローソク足の組み合わせだったらどうでしょうか。例えば・・・

- 過去の高値を超えたタイミング
- ギャップアップの連続
- 窓開け陰線コマが発生
という場合。このチャート状況を考えると、
- ギャップアップの連続は「三空踏み上げ」という考え方の過熱感
- 窓開け陰線のコマは「宵の明星」と呼ばれる天井圏の示唆
である可能性がありますよね。もしかしたら高値突破で力尽きたのかもしれません。
宵の明星はコマのあとに窓開け下落がきたら確定します。したがって、翌営業日の始値は相場への影響が大きいですよね。実際に・・・

翌日の始値はギャップダウンで始値をつけ、そこから軟調なザラ場になりました。このように「前日までの流れを加味して始値を考えること」でザラ場の流れを予測することも可能です。
まとめ
いかがでしたか?今回は始値の決まり方や重要性をお伝えしました。基本的な概念ではありますが、始値からは色々なことがわかります。ご自身でも色々と考察してみてはいかがでしょうか。
関連記事には
がありますのでご参考ください。