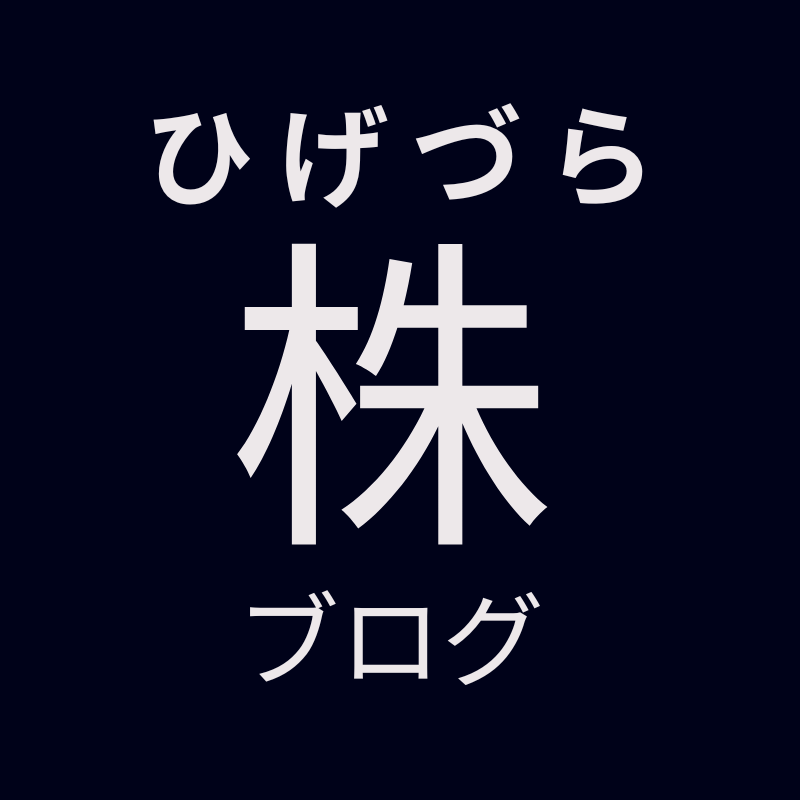どうも、ひげづら(@higedura24)です。
個人投資家、特に小型株ばかり買っている人は「塩漬株」のひとつやふたつお持ちだと思います。
塩漬株とは「含み損のまま保有を続けている株」のことで、いわゆる損切りを出来ずにいる状態です。
この背景には
- いつか含み損がなくなるのではないか
- 自分が損切りしたあとに株価が戻ったら嫌だ
- 含み損は確定しなければ負けではない
といった考え方がありそうですが、果たして本当にその塩漬株は復活上昇に成功するのでしょうか。
この記事では塩漬株の復活に成功しやすい例とそうでないものについて考えを述べました。
色々なパターンがあり思わぬ形で含み損がなくなることもあるのですが、ひとつの考え方としてぜひご参考下さい。
塩漬株からの復活上昇に成功しやすいパターンとは
今回ご紹介する「塩漬株からの復活上昇に成功しやすいパターン」は3つです。
早速ですが、それぞれに対してなるべく実例を挙げながらわかりやすく説明していきます。
1株益が維持もしくは向上している
そもそも塩漬株の復活とはどういったことを言うのでしょうか。
利回りの向上などもひとつの考えだと思いますが、一番わかりやすいのは「保有時の株価まで戻る」ということですよね。
株価が平均取得単価まで戻れば含み損は消えるわけで、粘り強く保有した結果として損失が出なかったのであれば万歳三唱となります。
株価が保有時の価格まで戻るためには株価が上がらなければならず、そのためには株式の本質的な価値が向上してくれなければなりません。
一般的に株式の価値とは1株益のことを言いますので、
- 事業が保有時から順調に成長している
- 業績が少しずつでも上昇して、1株益が上がっている
という状況であれば塩漬株の復活に成功する可能性はあるでしょう。
逆に自分が保有を開始した時期から業績がどんどん落ち込んでいるというケースでは、1株益が下がっているということなので「事業が上向かない限りは塩漬株の復活には成功しづらい」と考えられます。
例えば、日本たばこ産業(JT)は

このようなケースでは1株益の毀損が止んでくれない限りは大きな株価上昇が見込みづらいと思います。
もちろん株価上昇に必ずしも業績が伴っているわけではないですが、「株価上昇+1株益の向上」は基本概念としてまず考えたいことです。
したがって、根本的にはそもそも業績の向上が期待できないような株式は保有するべきではないとも言えますね。
塩漬株の復活を祈るのであれば、スタートとしてまともな株式を選ぶことです。
ちなみに1株益は証券会社のアプリで四季報欄を見れば上記のように誰でも確認できます。
業績が安定している大型株
まともな株式の代表格として業績が安定している大型株があります。
株本の中には大型株はやめときなさいという内容を述べた本もあるのですが、個人的には中大型株から銘柄選定することは間違っていないという考えです。
確かに投機的な観点では大きな値幅が生まれづらいでしょう。
しかし、株式を資産として保有するのであれば
- 価値がある程度定まっている会社ほど価格水準をイメージしやすい
- 株価も安定的で、多少下げても回復しやすい
といったことが言えます。
わかりやすく言えば「株価が長年1万円台だった銘柄が1万円を切った」となれば買う人も多いですよね。
そこには
- この銘柄は1万円台が当たり前だ
- 1万円を割り込むなんて滅多にないから安いことがわかりやすい
という考えがあるはずです。
なぜ株価が下がったのかにもよりますが、地合いによって事故的に下げただけなのであればなおさら買いやすいでしょう。
このように中大型株では市場にある程度の相場観が備わっているので、割安や割高の水準がわかりやすい特徴があります。
もしそういった株を塩漬しているのであれば、ある程度のところで下げ止まったあとに復活上昇するケースも十分に考えられるでしょう。
また、大型株は地合いに左右されやすい特徴があるので指数が上向けば連れ高となって株価が回復することも望めます。
実際に2012年のアベノミクス以降に作られた大型株の塩漬けであれば、日経平均株価が2018年まで上昇したことで解消されたはずです。
ところが、これが「新興株の急騰を高値掴みしたケース」となれば全く話が違ってきますよね。
場合によっては企業実態の何十倍もの価値で掴んでいるケースもあり、塩漬株の復活に成功する可能性が限りなく低いことがあるわけです。
そういった塩漬株が復活するとしたら、どこかのタイミングで仕手株の対象とならない限りは難しいかもしれません。
例えば、一時期何度も話題になったメタップスという銘柄の週足を見てみましょう。

この銘柄は年単位で何度も浮き沈みがあり、その度にちょっとした話題となった経緯があります。
見てわかるように2016年から数年間は値幅がものすごい事になっていて、平気で株価が40%以上も上げ下げしていますね。
おそらくこの流れの中でメタップスを塩漬した個人投資家は多く、実は私の友人もその一人でした。
その友人は100株しか持っていなかったのでまだ良かったのですが、一時期は10万円を超えるほどの含み損だったようです。
幸いなことに高値に戻るタイミングがあったので処理できたようですが、そこまで1年以上かかったとのこと。
また、図には載っていませんがメタップスの株価はさらに急落して500円台となっていることにも着目したいですよね。
メタップスの場合は明らかに企業価値よりも割高でしたから、友人も少しタイミングが悪ければ未だに何十万もの含み損でもおかしくないと思います。
中大型株ならまだしも小型株にはこういったリスクがつきものなので、塩漬株の復活を狙うには相応の覚悟が必要でしょう。
カタリストがある
株価上昇には業績向上が備わっていることが一番ですが、投資家としては業績が上がる前に先回りしておきたいという考え方もあります。
したがって「業績が上がるであろう要素」を持っている銘柄も人気が出るわけです。
こういった株価が上がる要素をカタリストと呼び、材料持ちの銘柄ほど塩漬株からの復活に成功する確率は高いでしょう。
株価は業績が悪くても一過性に需要が集まれば上がりますので、それを見計らって処理するイメージです。
限度はありますが、新興株なら思わぬ株価上昇によって塩漬株の復活に成功するかもしれません。
ただし、このカタリストは「新規で発表された」ということがミソだと思います。
例えばゲーム株では・・・

このように新タイトルのリリースに先立って株価上昇することがありますよね。
この時の上昇はすさまじいですが、高値から急降下するタイミングでは大量の塩漬株が出来上がります。
ここから塩漬株が復活するタイミングとしてよく考えられるのが「どうせリリースされれば株価は元に戻るだろう」というものです。
しかし、実際にはその前段階の上昇でリリース後の人気まで織り込んでいれば株価は出尽くしで下がってしまうことも多いでしょう。
したがって、高値から急降下したあとに「追加で新しい材料が出てくる」ということが必要なのかなと感じます。
新規材料によって市場の期待値がアップデートされれば上値が広がる可能性もあり、一時的にでも株価が戻る可能性はあるでしょう。
ただし、これは狙えるものではないですし出たとしても自分の平均取得価格まで戻るかはわかりません。
期待値としては薄い部類なので、塩漬株の復活に成功するかは神頼みの域ではないでしょうか。
<関連記事>
塩漬株の復活を成功させるための買い増しはあり?
ここまで塩漬株から復活するケースについて述べてきましたが、より早く取得単価まで戻すために含み損のまま買い増しする考え方もありますよね。
いわゆるナンピンというやつで「取得単価をなるべく下げることで含み損から早く脱出しよう」というわけです。
ナンピン買いは確かに取得単価が下がり、買い増さないケースよりも少ない上昇率で塩漬株を解消できます。
ただし、買い増した分だけリスクも増していることを忘れてはいけません。
個人的には、状況を総合的に考えて「復活の見込みが明確にある」と感じない限りは下で買い増しすることは危険だと考えています。
また、あまりに保有株数が多い場合にはちょっとやそっとの買い増しでは平均取得単価を下げることもできないでしょう。
仮に取得単価と現在値の間を取りたければ同数の買い増しが必要なので、ナンピン買いのリスク度合いも状況によると思います。
- 新興株なのか業績安定の中大型株なのか
- フェアバリューなのか成長株なのか
- 配当や優待など利回り面は期待できるのか
といった銘柄属性も関係しますので、ご自身でしっかりと判断をして覚悟のある買い増しが求められますね。
まとめ
いかがでしたか?今回は塩漬株からの復活に成功しやすいケースとそうでないものについて述べました。
やはり塩漬株が復活するには
- 株式そのものの価値が上がっているか
- 時価総額はどれくらいか
- 上昇要素はあるか
といったことが大事だと思います。
一番危険なのは小型株の急騰につられて天井高値で保有してしまったというケースで、その場合は厳しい戦いになりそうです。
買い増しするにしても明確に復活の見込みがあると感じられない限りは慎重に対応した方が良いでしょう。
関連記事には
がありますのでご参考ください。それではまた!